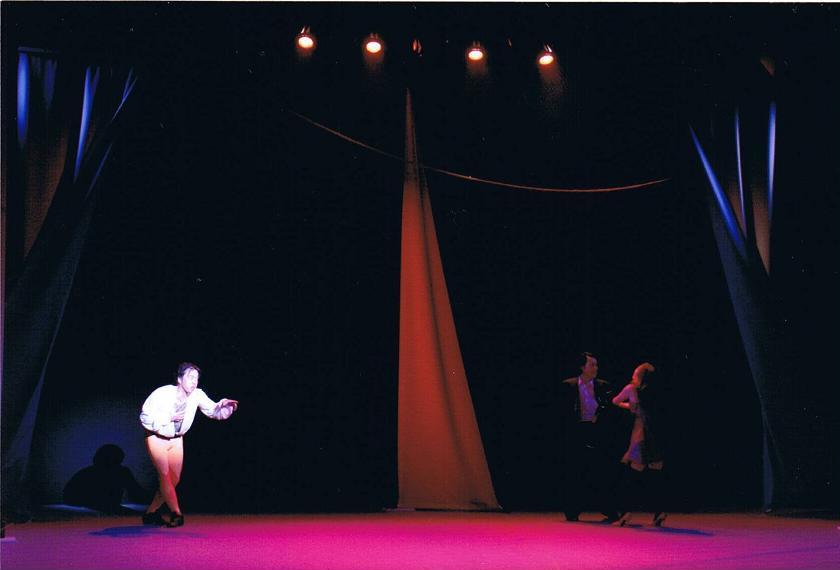≪Information≫
〇「生きた時間」、もちろん、それは「通俗的な時間」とは全く異質のものである。中井正一は、山本安英さんの「鶴によせる日々」のある現実体験の文章から、まさにワイルドの言葉のように「今、見ていることが、最も神秘だ」と思われる瞬間がある。神秘と思えるほどあざやかな現実が突如現前にあらわれることがある。山本さんの場合も自然を通して認識の達しない深みにおいて、自分自身にめぐりあっているのではあるまいかと言っているが、そうであろうと思われる。山本安英さんと言えば、木下順二作の「夕鶴」の舞台を思い出される方も多いであろうが、漱石に、娘が年頃になったらまず読ませたい本とまで言わしめた長塚節の小説「土」の舞台の主演女優も山本安英さんである。その舞台を観て女優の道に進み、名を成した方もいる。やはり、きっかけも含め、その人間の精神的基幹、形成に影響を与えるものの質の重要性を改めて、痛感せざるを得ない昨今である。
「訣別する時に、初めて、ほんとうに遇えたのだ」、それは、弛緩した時間の中でとぐろを巻いている状態とは全く異質の、自分への対決を経ずしては成し得ないものである。
2021 2/23
〇「火焔の王ー欠史八代の謎を読み解くー」(橋本ルシア著)は面白いだけではなく、極めて刺激的である。それは明快な哲学的思考に裏打ちされているだけに、生々しく現前に古代世界が立ち現れてくるのである。軽く読み流せる本ではないが、各章をオムニバスとして読むことも可能で、興味のある章から読めることも日々追われている者にとってはありがたい。
早速、アマゾンの「レビュー」などに現れた反知性の典型、リテラシーのなさは一目瞭然、「一代ズレたまま思込みひどく云々」などからも本書を読んでいないことがわかる。こういう人々がカルトの信者のような思込みで組み立てていることはすぐにそれと知れる。極めつけは、「タタラを韓国語で『豊』と述べられているが、韓国語はハングルで漢字じゃないでしょ?」、ハングルができたのは1446年(公布)以降、これは3世紀前後の話である。こういう者たちがもっともらしく嘘を蔓延させるのである。
追記:「フラメンコ、この愛しきこころーフラメンコの精髄ー」(橋本ルシア著)も、今年新装版として出版されている。著名な舞踊評論家の言った通り名著となっていた。 (この本について、正当に評価し得る能力のある者はいないと思っていたのでこれは意外でもあった)
そういえば、このフラメンコの本も出版当初は、半可通の人々がしたり顔で自らの無知をさらしていたことを思い出した。「フラメンコで生きる」ことしか考えていない者たちが「フラメンコを生きる」という著者についていけなかったのである。
〇-1 反知性の読解力の欠如した欺瞞に満ちたピンボケレビューや半可通の知ったかぶった物言いを見ていると、人間の救いようのなさも感じるが、逆に、やはり著者は並ではないなと思えるだけである。要するに、誠実でない何者かに取りつかれたような凡俗には、天才的な領域にいる人間を理解することは不可能なのである。そこには100年、万年の差がある。
2019 7/31
〇-2「火焔の王」、この本は実は怖い本で、知ったかぶって下手なことを言うと自らの無知をさらすだけということになるのである。天動説の世で地動説を唱えている、すなわち盲信者ばかりの領域で真理を追究しているようなものであるから大変である。否定、無視は無知蒙昧であるが故にたやすい、それに既得権益が加わればさらに捻じ曲げられる。ただ、無心に、誠実に関わりえたものには見えてくるものがあるということである。
2019 8/1ー
〇-3 確かに、この本は難しい。ライトノベル、漫画に慣らされた頭ではとてもついていけないところもある。しかし、やはり、面白い。因みに、私は3回目の読み直しに入っている。
2019 8/17
〇-4 すべて出版されれば全8巻にもなる原稿を、今回この「火焔の王」として一冊にまとめたというのであるから当然難しくもなるであろう。このサイトでも、以前「天才は始原を求める」と題して(2010 7/29)、著者橋本ルシアについて書いたことがあるが、今、それを思い出している。
※「天才は始原を求める」はウェブでそのまま拾える。
2019 9/12
〇-5 やはり、この「火焔の王」は、単なる「記紀」の盲信者(ネトウヨレベルは論外、埒外)ではとても読み解けるレベルの本ではない。国語学者の大野晋ですら「記紀」に対する捉え方が甘いのであるから後は推して知るべしか。
2019 9/23
〇誰もが行きたがらない漆黒の闇の中を、松明の光を頼りに渉猟し、真理を求め歩み続けた著者は称賛に価する。本当の本物である。これもまた一事が万事なのであろう。
2019 10/6
〇この本については、本屋に行ったが置いていないので、郵送してほしいと現金書留を送ってくる方、また、地方の本屋で注文すると1週間以上はかかるといわれたのでそちらから早く送ってくれないかということもあった。「てんびん社」の推薦図書にもなっているので「てんびん社」から何回か郵送したこともある。因みに、紀伊国屋書店レベルの本屋でないとこの本は扱っていないだろうと思われる。漫画、アニメ、ラノベの類で糊口を凌ぐ本屋にはあろうはずもないのである。
2019 5/20ー6/4ー7/25ー7/31ー8/1ー8/17ー9/12ー9/23ー10/6 2020 1/18
※本が読めていない身の程知らずのレビューについては、著者・橋本ルシアが自身のサイトのインフォメーションで具体的にその問題点、誤りを指摘している。
橋本ルシア 断章
右手にスピノザ、左手にデカルト、頭にシェリングの髪飾りをつけて、天を仰ぎつつ舞っていたというのが東京大学文学部哲学科在籍時に行きついた彼女の姿である。所詮、己を知らない者たちの凡俗な浅知恵で太刀打ちできる相手ではない。要するに、素地が違い過ぎる、文化レベルが比較にならないのである。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇現在でも、SPAC-静岡県舞台芸術センターとSCOT、舞台芸術財団演劇人会議から毎回その上演案内と招待状が届く。何度か行ってみたいと思う作品があったが、時間が取れなかった。おそらく近くに住んでいればそのすべてを観ていたであろうと思われるくらいである。今回の「イナバとナバホの白兎」も場合によってはパリで観ることにもなったかもしれないが、静岡芸術劇場で観ることになりそうである。
帰りがけ、受付付近で「太陽」に会った。「お疲れ様」と呟くと「太陽」も何やら呟いていた。
2019 5/4ー6/9
〇演劇が、ある意味一期一会の「縁劇」でもあるのなら、ピエール・ノット作の「北をめざす二人のおばさん」は市原悦子と樹木希林の出演で成立もしていたであろうと思われる。私の頭の中ではその舞台は完璧に出来上がっている。舞台上での彼女たちの会話、しぐさが急にたち現れ、思わず微笑みさえ出てしまう。その一挙手一投足が人生の一瞬の輝きを見せて消え去っていくのである。これは彼女たちが亡くなってしまったからそうなのではない。もし上演が実現していたら、彼女たちならパリでも絶賛されたであろうと思われる。しかし、今は、私の頭の中だけで生きている。これは私の知られざる傑作の一つでもある。
追記:2009年4月シアターχで、私の演出で上演された「北をめざす二人のおばさん」を観た方の中には、私とその感覚の一部を共有できる方がいるかもしれない。この舞台に関しては、ピーエル・ノット自身の二人の女優を含めた舞台全体についての評がこのサイトにも載っているのでここではその詳細は避ける。
2019 1/18
追記2:「縁劇」で思い出したので、一つの具体的事例を挙げると、1980年アトリエ・フォンテーヌで仲谷昇の主演で「雌山羊が島の犯罪」(作ウーゴ・ベッティ 演出 平山勝)を上演した時も、これは、仲谷さんがまず私の提示した作品に乗ってくれこと、そして、その時期の様々な要因が重なり合って成立した上演作品でもあるということである。すなわち、一期一会の「縁劇」なのである。俳優・仲谷昇氏の普段見られぬ一面についてはこのサイト(2009年4月以降の(「五叉路」)でも少し触れているのでここでは避ける。そして、その当時、演劇専門誌「テアトロ」の編集長をしていた翻訳者でもあり演劇評論家の利光哲夫氏、どこで会ったか覚えていないが開口一番「どうして上演することを教えてくれなかったのか」と興奮気味に私を責めたのを覚えている。私としては他意もなく、失礼するつもりもなかった。煩雑な制作過程に追われている内に失念してしまったのであろうと思われる。(「普通の制作者」であれば喉から手が出るほど欲しい接点であったであろう)。今でもあの作品は上演したかったができなかったという演劇関係者の話を聞くことがあるが、そんな時、リュート奏者つのだたかしに作曲してもらった主題曲がどこからともなく流れて、舞台下手の大きな井戸と、夕陽が格子窓越し差し込んでいるのが見えてくる。
この作品は、再演の強い要望もあった作品で、2005年にシアターモリエールで中村ひろみなどの若手で上演した(演出・美術・音楽 平山勝)。1980年の上演時のスタッフは、美術 孫福剛久 音楽 つのだたかし 音響 深川定次
〇樹木希林については、マスメディアが騒がしいので暫く時間が経ってからと思っていたが、岸田森について語っていた賀原夏子のことも思い出されて巷間の雑音とは無関係に忘れないうちに書き記しておこうと思った。賀原夏子も岸田森も樹木希林も元文学座の座員である。1980年前後であったかと思われるが賀原夏子は私に、「岸田森はいいよ、いい役者になった」と言ったことがあった。その言い方、表情に何かただならぬ思いが込められていたのが印象的であったのである。それは岸田森が43歳で亡くなる2,3年前のことである。岸田森も樹木希林も賀原夏子たちが三島由紀夫の「喜びの琴事件」で退団する一年前に文学座に入団している。その後のことは周知のことであるから端折るが、特に最晩年の数年に樹木希林が到達し得た己を徹頭徹尾虚しくした自在な境地は本人にとって何にも代えがたいものであったであろうと思われる。癌などはその媒体であったに過ぎない。これは「終活」などというコンセプトで捉え切れるレベルではないのである。
2018 9/19
〇ふと気になることがあって、高田保(たかだ たもつ)のことを調べていると「高田保伝」(榊原勝著 1982年)という本が出てきた。その中に「高田保は『ブラリひょうたん』(エッセイ)がなくても、日本演劇史にその名脚色名演出によって名をとどめている人と云われている。昭和54年5月15発行の劇団機関誌に座長賀原夏子と演出家平山勝の『対談』の中に、賀原ー <つい最近、装置(美術)の三林亮太郎先生が『演出家で一番すぐれていたのは高田保です』とおっしゃたのを伺って、何だかすごくうれしかった。私が喜ぶのも変だけど(笑い)>とある。」 高田保についてはこのサイトでも断片的に取り上げてきたが、私が二コラ・バタイユにパリでやってみないかと言われたのもこの高田保の作品である。その時のことがまた甦ってきたのである。日本語のあまりわからないバタイユが上演された高田保の小品のエッセンスを見事に捉えていたのには驚かされた。日本の演劇人ですら高田保の小品群についてはほとんど知らないと言ってもよいだろう。現に賀原夏子でさえその当時まで知らなかったのである。
※二コラ・バタイユ:イヨネスコの発掘者でもあるフランスの演出家・俳優。
因みに、大宅壮一(社会評論家)は、高田保を評して「かれは銀座裏の良寛であり大磯の一茶である」といっている。そこに実用主義、功利主義、権力主義、出世主義に対する無言の抗議、レジスタンスをみて好感以上のものを持つ者も多かったのである。彼の才能が多方面に渡ることは広津和郎(作家)も驚いているほどである。
2018 8/5 8/19
〇芸術一般は、コアな領域があればあるほど作品自体は「反権力」にならざるを得ないものがある。単に大衆に媚び、権力に媚びる者とは、どちらにしても「芸術」領域からは乖離するのは必然で、単なる「興行師」、「起業家」、「企業家」の類であってそれ以外のいかなる者でもない。最近、時の権力者とも親しい関係にあり、自己の劇団を「企業」として大きく成長させた「社長」、「興行師」が亡くなったが、彼が「演劇界」で、否、演劇そのもの中で一体何をなしたのか?少なくとも、「演出家」として刮目に値するものは何もない。
ただし、一言付け加えれば、浅利慶太が国からの叙勲をすべて辞退したということは、そこに唯一演劇人としての残されていた気概のようなものを感じた。以前、杉村春子が文化勲章を辞退し、自らの経緯に殉じる「凄み」を見せたのに、蜷川幸雄の文化勲章受章の喜びようにはあまりにも俗っぽい軽さを感じたことなども思い出された。本来ならこれは逆であろう。
2018 7/18 +21
〇いまだに、ブログなどでも匿名で舞台についての「批評」、「感想」の類を書き綴っている者がいるが、やはり無責任である。私などは匿名というだけでまったく信用していないので無視しているが、「演劇批評」などは社会・政治批評のように権力者などに睨まれることもない内容であろう、それでも匿名というのは何を恐れているのか不可解な面もあるので、なぜ匿名にするのか是非聞いてみたいものである。昨今でも、もっともらしい内容で人々を誘導し、結果的には間違いであったことがばれて弁護士に提訴された事例があったが、やはりどのようなものでも「真摯なもの」を発信するのであれば「匿名ではないこと」が必須条件である。匿名の「批評」、「批判」、「デマゴギー」類などに振り回されていると今後はますます取り返しのつかないことにもなりかねないというのが実情である。ただし、「B層」などに分類されない方々、分析能力、直感力もある方々には言わずもがなのことであろうと思われる。
2018 6/11
〇坂口安吾に言わせれば、「新聞記者だの文化映画の演出家などは賤業中の賤業」で「彼らの心得ているのは時代の流行ということだけで、動く時間に乗り遅れまいとすることだけが生活であり、自我の追求、個性の独創というものはこの世界には存在しない。」、「要するに、この連中には内容がなく空虚な自我があるだけである。」云々ということになるが、これは今なおマスメディア一般の在り様そのままであろう。「文化映画の演出家」とは当時の軍部の検閲も通るようなものを嬉々として作る者と言う意味でもあるが、今では「現状」におもねる視聴率第一主義のテレビの演出家、ディレクターなどもそれに該当する。このことは以前にもエッセイに書いたが、そのような意味では私は「演出家」にはまったく向いていないどころかそれこそ乖離しているが、「演出」が世界観の現存在を通した再構築という意味なら「演出家であること」も了解できる。
2018 5/31
〇久しぶりに観たいと思う舞台の案内が来ていた。「繻子の靴」(作・ポール・クローデル、演出・渡邊守章)の舞台である。上演時間8時間の超大作である。招待状も戴いているので何としてもと思っているが果たして行けるかどうか・・・
その他にも、劇的舞踊「ROMEO &JULIETS」、音楽劇「マハーバーラタ」などの案内もきていた。どれも本当の意味での「演出」(世界観)の醍醐味を感じさせる舞台であろう。
2018 5/27
〇舞台については、現実の煩雑な「手続き」、そして直接的な「関与」などが乏しい表現にかける時間などを考えると、舞台は「自らが想像し」、「自らがつくれば」それでよいと思っている。「コアなもの」を感じさせないものに興味のない私としては「コアなもの」の舞台化が現実的にますます困難になっている現在、これもまたごく自然な流れであると思っている。
2018 5/11
〇最近また「吹き替え版」の騒動が起きたようだが、当然であろう。アニメならともかく外国映画の吹き替え版は私は決して観ない。味覚障害になったように本物の「味」がわからなくなるからである。試しに目を閉じて声だけを聴いてみるとよい。それで何も感じないようなら「似て非なるもの」に完全に慣らされているということである。私の友人に声とその言語の遣い方だけでその人柄を的確に言い当てる人がいるが、「吹き替え版」などは「とても耐えられない」と言う。因みに、俳優でもない声優は顔を出すべきではない。それは大いなる勘違い。
2017 8/20
追記:要するに「声の身体性」の欠如である。
〇昔、多少の縁あって、舞台作りも共にしたことのある俳優が舞台から転落死した。大動脈解離だそうである。彼がどのように落ちたかも具体的にイメージできるから不思議である。死は、緩慢なる死ばかりではない、ある日突然やってくる、常に老少不定。しかし、舞台でそのまま死ぬとは、蓋し役者としては本望なのかもしれぬ。
2017 7/8
〇俳優・中村敦夫(77歳)が自作の原発問題を扱った朗読劇「線量計が鳴る」をもって全国をまわっている。この年齢になると毎日が戦場を歩いているようだとも言っているそうである。このような役者がいることに同時代人としても共感以上のものを感じる。因みに、紋次郎も「あっしにはかかわりねえこって」と言いながら、かかわらざるを得なくなったことには命がけで戦っていたと記憶している。義を見てせざるは勇無きなりというところでもあろう。この役者のスタンス、問題意識にも昨今の義のない有象無象ばかりを見続けた者にとっては素直に共感し得るものがあるのではないか。
〇作家、映画監督なども世界観はもちろんのこと、やはり明確なスタンスを持っていなければ話にならない。それもさらに展開し得るほどの強靭な「核」がそこになければならない。役者やお笑い系の者がその気になって撮っただけの映画などに観るに堪えうるものがほとんどないというのも、問題意識、スタンス、世界観の脆弱さが露呈してしまっているからである。金の出どころばかりに嗅覚がはたらき、その挙句に「肝心なもの」がつぎはぎだらけになっているのに気づかない者はいくらでもいる。
〇2017年2月23日に、日本劇作家協会が「新共謀罪」に反対する表現者の緊急アピールを行っている。当然であろう。少なくとも芸術領域に身を置く者がこのようなことに「無感覚」、「無関心」では話にならない。賛同団体として、日本新劇製作者協会(2/23付)、国際演劇評論家協会日本センター(2/26付)、公益社団法人日本劇団協議会(3/4付)。
誰が何をどのように考えているかなど知る由もないが、言動と金の流れで「その在り様」はわかる。沈黙、回避は雄弁にその者の在り方を物語っている。
※様々な形でその都度、意思表明をしている表現者もいることは確認できた。よりよき表現主体となりうることも期待できそうである。
2017 3/10
「共謀罪法案」の反対表明を日本ペンクラブも行う。(4/7)
国際ペン(本部・ロンドン)が6月5日に共謀罪に反対声明を発表。国際ペンは世界102か国144センターを組織する文学団体のトップ。会長のジェニファー・クレメント氏が「共謀罪は日本の表現の自由とプライバシーの権利を侵害する」と題する声明を読み上げた。これで世界が日本政府の意図をさらに厳しい目で注視することになった。
※国際ペンの会長が日本政府に声明を出したのは二度目である。前回は特定秘密保護法制定の時、同一政権下で二度目とは異例で、それだけでも異常事態であるということである。
〇メディアのみならず知識人といわれている者たちですら、「演出」という意味をほんとうには理解できていないことがよくわかる場面に出会うことが多い。特に舞台で遣われることが多い「演出」という概念自体がいつの間にか皮相な「効果」、「小細工」、「ごまかし」、「目くらまし」などの矮小化された意味に収れんされていってしまったのであろう。メディアの社会面などで少し大衆の目を引くことが起きると「〇〇劇場」など出てくる。そして、それに呼応するかのように小賢しい、ごまかしが見えてくるとそれを「演出」などという言葉で括るのである。この一連の何気ない動きそのものに概念規定の曖昧さ、すなわち、思考の「あまさ」、文化程度がにじみ出ている。大方が、それで何か言い当てているつもり、何かわかったつもりになっているのであるが、実は、何も捉え切れていない、わかっていないのである。軽佻浮薄な「陰謀論」、「自虐史観」などという曖昧「概念」とたいして変わるところはない。
2017 3/8
因みに、いまだに演出と舞台監督の区別もつかないのがメディア、一般の実情である。
〇「演劇を愛する」という者、鏡の前で己に問うてみてはどうか。それは演劇そのものに対する「愛」なのか?それとも違う単なる欲動(自己顕示欲も含めて)なのか?「演劇を愛する」ということが彷徨える「遁走狂」の一時しのぎではないとどこまで言えるのか。ついそのような心境になってしまう相変わらずの昨今の演劇事情である。一向に深まりようのない吹けば飛ぶような屁のような演技、どこでかき集めて来たのかわからぬような舞台とは無縁のスタッフ等々。現状のサイクルに従い、深い轍にはまっているようでは到底抜け出すことはできまい。役者としての「存在証明」と何もしないことに対する強迫観念だけが「キープ」を支えているとするなら何とも愚かしいことである。それは「演劇を愛する」こととも隔たりがあり、無に等しいというよりも、無よりも「質」が悪い。敢えて言えば、演劇従事者、役者としての「存在証明」などというより人間としての「存在証明」の方が先であろうということである。そこら辺が希薄だから迫力に欠けるとも言えるのである。要するに要領のよさと損得勘定だけが透けて見えるのである。もっともキッチュに慣らされた大衆にはそれでいいのかもしれぬが、それでは先に進めない。それ以上のことが望めないということは縮小再生産の負のスパイラルから抜け出すことはできないということである。
私の知らないどこかで、そのようなことが着実に裏切られていることを期待している。
2017 1/某日
〇「蜷川マクベス」等々、やはり「宝塚」が成り立つ国のお話しであろう。そう言えば、かつて二コラ・バタイユも「宝塚」の演出をしたことがあったが特にバタイユである必要もなく、「名前貸し」に近いものであった。「オフ」から始まり「オン」に関わる「演出家」の、その経緯とその限界の様相を改めてまざまざと見せつけられた。日本の民度とはやはり「AKB」が象徴しているとしか言いようのない現状なのである。それは、すべてにおいてそうである。それではどうすべきかなどと各論的なことばかり煮詰めてもただ煮詰まるだけである。そうかと言って根本から捉え直すなどと言ってみたところで言ってみただけの話ということにもなる。要するに、具体案を出せと言われて出せる程事は容易ではないから多くは「流れていく」のである。「流されていく」のもそれは一つの選び取り方でもあるが必然的にいかがわしい面も取り込むことになる。後は時間に任せるより手立てはないということでは現在の日本の「民主主義」と同様、立憲主義はいつのまにか外見的立憲主義に移行しているということにもなりかねない。時間任せ、風任せでは行きつくところは目に見えている。「芸能人」、「演劇人」とは歴史の埒外にあり、「穢多・非人」と同一であるなどと言いたいわけでもあるまい。それほどの意識があればまだ良い方だが、多くは単に損得勘定レベルの右往左往というのが実情であろう。「沈黙は金」とばかりの小賢しい「外し方」、「縫い方」自体にすでに問題があるのである。死ぬ間際になって、いくら真摯に訴えてももう手遅れなのであるが、少なくとも自分には嘘はついていなかった証にはなろう。もし、自分をも騙しているのなら完全に「サイコパス」である。「サイコパス」は何とでも言うし、言い逃れもする、嘘を嘘とは「思えない」からである。嘘を常に醸造することでしか生きれない有機構造体ともいえる。通りがかりに選挙の掲示ポスターやら、大写しの宣伝広告写真を見る度に「気違い病院」を想起するのは何も今に始まったことでもない。
2016 7/21 ー蜷川追悼番組が多い昨今にー
〇以前、この世界を「精神病棟」と称した演出家がいたが、すでにパスカルは「パンセ」のなかでこの世の比喩として「un hôpital de fous」(気違い病院)という表現を遣っている。私も、事ある時に限らず、そのことを痛感しざるを得ないのが実情である。
2016 7/15
〇1週間程度の、中には3,4日位の、それも小劇場で公演する意味がどれほどあるのか。多くは内輪のパーティ以上のものではないが、個人間では多少の「効用」もあるのであろうと思われる。だから、やっているのであろう。しかし、第三者にとってはほとんど無意味に近い。そして、パラサイト系の「専門誌」がその公演を取り上げての毀誉褒貶、そのもっともらしい内容に大した根拠もなく一喜一憂するのが大方の実情である。これでは「上質なもの」が育つわけがない。これは大劇場の長期公演、新聞の演劇評がいいと言っているわけではない。同質である以上、大中小は関係なく、同一の問題が横たわっている。
それにしても、メディアなどにも出て来る日本の「演出家」と称される者の浅薄そうな面の悪さ、どこの政治屋かと見間違うことがよくある。右翼ポピュリスト、走狗、三百代言などの顔が指名手配写真の照合のように脳裏を走る。実際、言っていることもあるようなないような、分かったような分からないような、コピペの域を超えるものでもなく、何より根幹部分で不誠実で信用に足るものではないことだけは明確にわかる。日本のどこをどう切っても一事が万事ということを再確認するばかりである。
演劇に、「継続」、「持続」自体を目指すことはまったく無意味、むしろ害の方が多い。過去の「夢」など再現する必要も意味もない。
2016 6/26
〇私は、字幕であれば何でもいいというほど吹き替え版は観ない。その理由については他のカテゴリーでも書いているのでここでは避ける。最近、また最後まで観てしまった作品の中に映画「夜の来訪者」(作・プリーストリー)があるが、このレベルの作品はやはり面白い。
2016 6/19
〇記憶というのも曖昧になりがちな上に、この≪Information≫にも入っていなかったので念のため改めて書き記しておく。「私もカトリーヌ・ドヌーブ」作ピエール・ノットの本邦初演は2007年4月のシアターχで、翌2008年2月「池袋あうるすぽっと」で再演された。近日中に参考のため舞台写真、ビデオなども載せるつもりである。
※カテゴリー「メッセージ」の8で「ピエール・ノット本邦初演4作品について」と題して当時の状況も交え、ある程度は書き記している。
2016 5/4
〇9月17日、ピエール・ノット作・演出の「私もカトリーヌ・ドヌーブ」を観た。今までとは息子の取り上げ方が違っていた。そこには「les gens qui tombent」(倒れ行く人々)を扱った作品を通して作者自身が自らを乗り越えようとする姿勢すら垣間見えたが、全体として作品自体に内在する日常的「狂気」が妙に収まってしまって、最後の母親「強い溜息」も何か日本的リリシズムに収斂されていくようにしか見えなかった。この作品のインパクト、収拾できないネガティブな様相も「うまく」薄められてしまっていた。それは日本人的味付けなのか、それとも別の事情があるのか、ピエール自身も褒めるくらい日本の俳優たちもがんばってはいたが、もはやそのような領域に留まっているわけにもいくまい。しかし、そこには個々の問題では解決、集約しきれぬ問題も隠されている。
ピエールの作品は単なる台詞劇ではない。いかに文法的に正確に訳されていても、たとえ名訳であたとしても、そして、それを舞台上で明確に伝え得たとしても、「何か」を感じさせる舞台とはなり得まい。作者が作品に託して発信している「核」ともなる「痛み」に同時代人として「共感」し、展開し得るものがない限り、内容を深めることも、軽快にすることもできない。要するに、より斬新な舞台は望むべくもないということである。なぜ、台詞を歌わせる箇所が多いのかを考えるべきなのである。それは、単にミュージカル志向からくるものでもなく、もちろん従来のオペレッタ的なものでもない。因みに、最近のオリビエ・ピーも台詞を歌わせることがある。
※「5.演出家・平山勝」の項目はこの辺りから許容量オーバーとなったようで、以前載せていた写真、文章が消えてしまっていた。できるところまでは元に戻すつもりである。(2016 7/15)
〇ピエール・ノットの「L'effort d'être spectateur」(「観客である努力」)と題したメッセージ性の高いレクチャーの中で「観客の仕事」について述べたところがあるが、このようなコンセプトは日本ではほとんど取り上げられることはない。怠惰な観客相手に「笑って、泣いて、楽しませます」というサービス精神に徹したような大衆蔑視、観客と作り手と負のスパイラルとも言える悪循環がただでさえ落ちている民度をますます降下させているのが多くの現状でもあろう。ピエールのレクチャー内容は全体的に自分でも日頃から考えていることと通底するところが多くあった。後日、彼と会って彼のプロジェクトの名称「Les gens qui tombent」がなぜ「tomber]なのか聞いてみた。それはあまりにも明解なものであった。彼からもらった「Rond Point」劇場の袋にはこう書かれてある。「ON NE VOUS EMPËCHE PAS DE CROIRE.VOUS NE NOUS EMPËCHEREZ PAS DE PENSER」。因みにこの劇場はテロ事件が起きたところからそう遠くないところにある。
それから、2015年のアヴィ二オン演劇祭のオリビエ・ピーの「リア王」を観ても、舞台はもちろんのこと観客層の厚さ、関わり方の相違は一目瞭然。それは端的に言えば、常に問いかけながら再構築しようとする底力を持つ者とそうでない者たちとの違いである。それは、「人生に対する関わり方」、「楽しみ方」の根本的相違でもある。どちらが人間を深化させ、本当の意味で進化に導くかは明白である。大衆の覚醒を恐れる者とは?それは言わずもがなのこと。私の立ち位置は少なくとも覚醒を妨げる側にはいない。
「あなた方が何を信じ、確信するかは自由である。しかし、我々の思考展開を妨げることのないようにしていただきたい」
※オリビエ・ピーとその舞台についてはこのサイトでも以前紹介を兼ねて取り上げている。
2015 9/1
〇2015年8月19日ー23日、「国際演劇セミナー2015」(4)フランス特集としてピエール・ノットが招聘講師として来日する。今後もこうした企画を通して「国際的な視野を持つ演出家、及び劇作家、俳優の育成」を望むところであるが、民度はそうやすやすと変わり得るものでもない。手の届くような距離にあると思えても実はとんでもない壁が聳え立っているものである。言ってみればどれだけその距離と壁に面と向きあい葛藤したかが国際的視野を成り立たせる要因ともなる。いつまでも「物まね」、「アリバイ作り」に終始していても仕方あるまい。
とにもかくにも、文化的営為は時間がかかる。そうかと言って立ち食い蕎麦屋でいつまでも蕎麦の講釈をしていても何も始まらないというより無意味であろう。
因みに、フランスでは小劇場クラスでさえ1週間程度の公演など皆無である。2,3か月の公演が普通で、それが常識的に成り立っている。このことだけでもどれだけ日本の演劇事情と異質か明確であろう。
〇2015年秋ごろ日本で、場所は忘れてしまったがピエール・ノット作・演出で「私もカトリーヌ・ドヌーブ」を上演するらしい。おそらく日本の役者有志が集まって製作しているのであろう。役者がフランス人であればピエールもその手腕を発揮することも可能であろうがどうであろうか。日本の役者を使ってフランスで上演されたようにやろうとすると、どうしても齟齬(そご)と間隙が生じるのである。いつかピエールが連れてきたフランス語の流れのように滑らかな動きをする高校生のレベルまでも難しのではないかと思っている。詩を文法的に直訳すのは中学生でもできるが、やはり詩人でなければ良い訳はできないのと同様に日本語に置き換えられる時点で、日本の現状の根幹部分に抵触する置き換え作業、同化と異化が同時に必要となってくるだろう。たとえば、フランス語で「息切れ」を意味する言葉をそのまま「息切れ」とするより、誤訳にもなりかねない「勝手にしやがれ」と訳した方がよりわかり易いと同時に直に伝わってくるものがあるというのも実情であろう。それは言語領域だけに留まることではない。
〇2013年 パリではピエール・ノット作品のプロモーションなどを目的としたカンパニー「Les gens qui tombent」が設立された。また、私の演出作品のよき理解者でもあるフランソワ・ラヴォー氏(パリ大学名誉教授)の人生とその人生観に興味を持ったジャーナリストが現在(10月)彼の口述を録音しているということである。
〇2013年4月27日(土)14:30?16:30 青山学院大学19会議室に於いて、ピエール・ノット作品日本公演(平山勝演出)の際に翻訳を手掛けたクローデル研究の泰斗でもある中條忍氏(青山学院大学名誉教授、前日本クローデル研究会会長)が「クローデルと日本、ー能との関わりをめぐってー」と題してレクチャーを行います。ご興味のある方はご参加下さい。
〇2011年3月3日、2010年6月に製作・監督した「月華独舞」をパリに送る。
4月12日、「月華独舞」について
<パリ評>
〇「日本伝統芸能にある幽玄のような感性を感じました。音楽も意外で、初めの音楽はワグナーのトリスタンとイゾルデの中にある序曲を思い浮かべさせられましたが、その後、最終部分以外は、日本の伝統音楽的な要素と踊りとマッチして、幻想的な雰囲気が描かれてとても魅力を感じました。踊り手の内に込めた情熱が徐々にリズムに乗って盛り上がるプロセスも素晴らしいと思いました。スペインの情熱あふれるものと日本の美を織り込んだ創造芸術。」
〇「映像技術も見事。Lucia Hashimotoの踊りは歌舞伎、能などを彷彿とさせ、その手や腕の動きからは東南アジアの踊りさえ思い浮かべさせられ、引き付けられた。」
<国内評>
〇「稀に見るフラメンコ映像詩」、〇「ただ、素晴らしいの一言」、〇「凛とした中に秘められた悲しみ、それでいて決して重々しさを感じさせない何とも言えない心地よさ」、〇「美しい」
※これらの感想、批評はいいものだけを集めたのではなく、このように感じうる人々がいたというという意味での参考である。後は単に民度の問題である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※2011年以前の掲載分については許容量オーバーで「メッセージ」の2と3に移動しました。